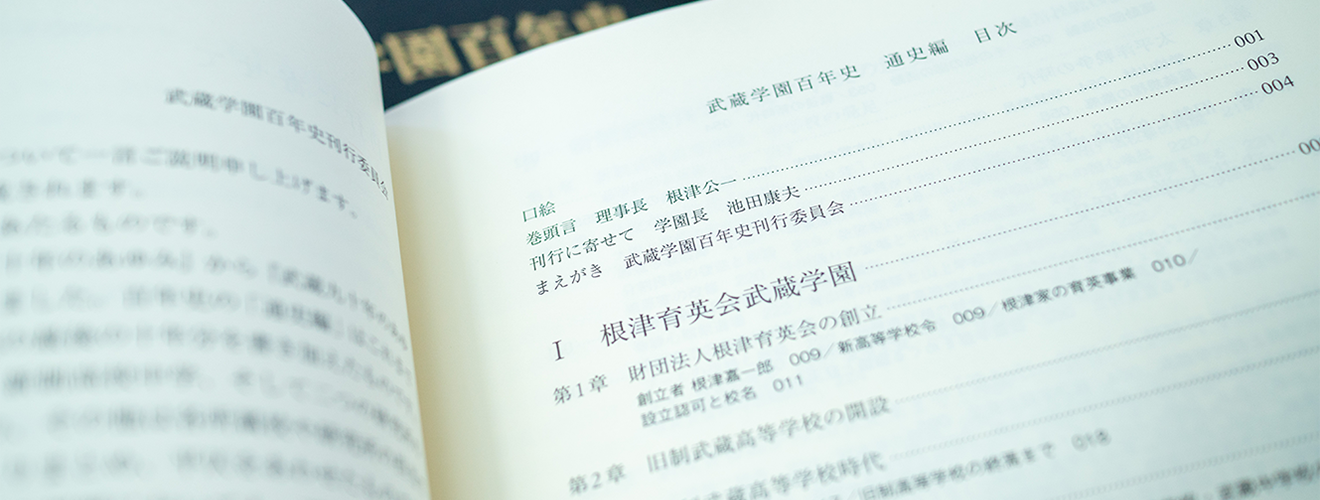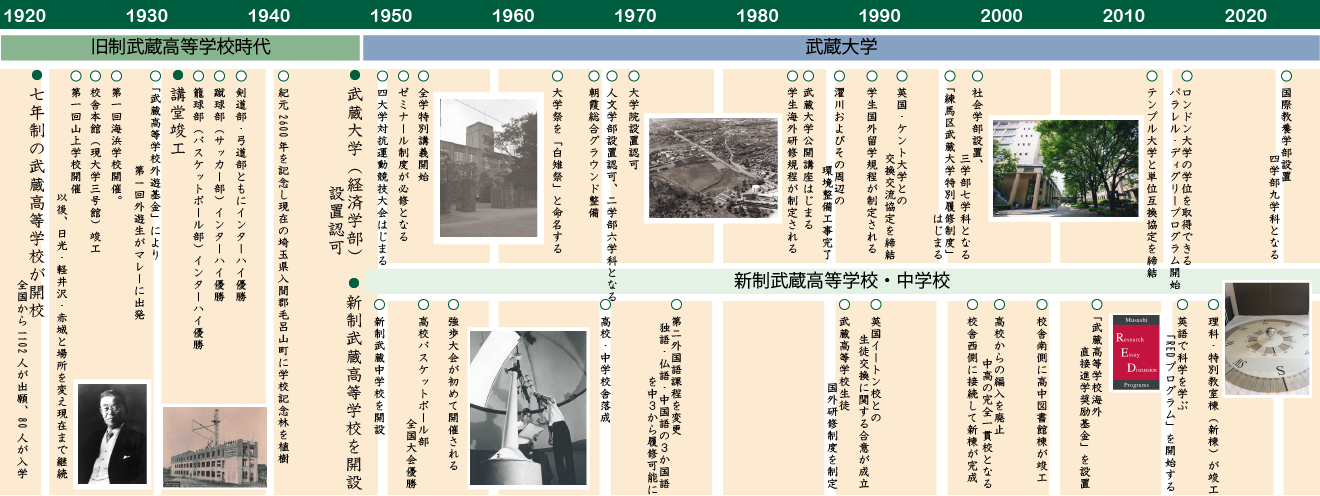資料で見る武蔵学園
これまでの百年と次の百年への展望
根津育英会武蔵学園は2022年4月17日で創立100周年を迎えました
根津育英会武蔵学園は2022年4月17日で創立100周年を迎えました
旧コンテンツ「武蔵学園史紀伝」は、「武蔵学園百年史」-「主題編」の同一名項目よりご覧いただけます。
更新情報
動画館
2026.02.05
動画館
2026.01.05
動画館
2025.12.05
TOPICS